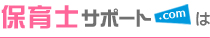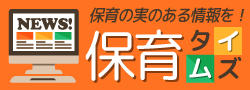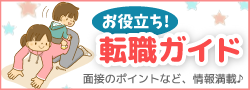保育士試験|オリジナル問題集
「子どもの食と栄養」part3
-
第28回
オリジナル問題集
登録日:2015/12/28
「子どもの食と栄養」 part3
問1
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
牛乳・乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで、カルシウムをとりましょう。(「食生活指針」(平成12年 文部省、厚生省、農林水産省))
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○
解説を見る
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
唾液に含まれる唾液アミラーゼはでんぷんをショ糖とブドウ糖に分解する酵素である。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
×
解説を見る
問3
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
水分は乳児で体重の80%、成人で60%を占める。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
〇
解説を見る
問4
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
エネルギー源としての炭水化物の特性は、脳、神経組織、赤血球など、ブドウ糖しかエネルギー源として利用できない組織にブドウ糖を供給することである。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
〇
解説を見る
問5
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
たんぱく質は、血液中において、脂肪や鉄などの栄養素を運搬する働きもある。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
〇
解説を見る
問6
次の文は、子どもの発育・発達と食生活について記述されたものである。誤って記述されているものを記号で答えなさい。
- 離乳の開始前の乳児にとって、最適な栄養源は乳汁(母乳または育児用ミルク)である。
- 生後7、8か月は、1日当たり全卵1/2個が目安である。
- 育児用ミルクでは、乳児の脳や網膜などの発達に必要な不飽和脂肪酸であるステアリン酸が強化されている。
- 離乳食開始の頃は、離乳食を飲み込みやすいように赤ちゃんの姿勢を少し後ろに傾けるようにすると良い。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
B
解説を見る
次の文は、子どもの発育・発達と食生活について記述されたものである。誤って記述されているものを記号で答えなさい。
- 通常、新生児では出生後の数日間、出生時の体重と比較して一時的な生理的体重減少がみられる。
- 乳児の胃の形状が徳利(とっくり)状に近いことが、乳児が溢乳や吐乳を起こしやすい原因である。
- 乳児は、3か月頃になると、指をしゃぶり始めるようになり、おもちゃを口に入れたりして遊ぶことで、食べる・話すなどの口の発達が促される。その為おもちゃなど、清潔に気を配っていきたい。
- 第一乳臼歯が生える頃には、咀嚼ができるようになる。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
D
解説を見る
問8
次の文は、子どもの発育・発達と食生活について記述されたものである。誤って記述されているものを記号で答えなさい。
- 母乳育児の利点の一つとして、出産後の母体の回復を促進することがあげられる。
- 通常の発育・発達を遂げている乳児の最も適切な離乳食の開始時期は、生後8か月以降である。
- 離乳食に慣れ、1日2回食に進む頃には、穀類、野菜・果物、たんぱく質性食品を組み合わせて食事にする。
- 12~18か月頃の食べ方の目安は、「1日3回の食事リズム・生活リズムを整え、自分で食べる楽しみを手づかみ食べから始める」とある。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
B
解説を見る
問9
次の文は、食育の基本と内容について記述されたものである。誤って記述されているものを記号で答えなさい。
- 食育基本法において食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成のために定められている。
- 食育基本法では、肥満や生活習慣病の増加・過度の痩身志向・栄養の偏り・食の安全上の問題・食の海外への依存・伝統ある食文化の喪失などを挙げている。
- 「学校給食法」では、学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とし、目標の一つに「食生活の合理化」が挙げられている。
- 健康な身体づくりや生活習慣病の予防のためにも、子どものころから「食育」を学び、食生活を自己管理する力を身につけることが重要である。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
C
解説を見る
問10
次の文は、家庭や施設における食事と栄養、特別な配慮を要する子どもの食と栄養について記述されたものである。誤って記述されているものを記号で答えなさい。
- 食中毒予防の3原則は、食中毒菌を「付けない」「増やさない」「やっつける(殺菌する)」である。
- 保育所では、予定献立や連絡帳を活用し家庭との連携を十分にとる必要がある。
- 「えび」「かに」を原料とする加工食品においては、食品衛生法施行規則により、これらを含む旨を容器包装または包装の見えやすい場所に表示することが義務づけられている。
- 幼児期の肥満は、成人期の肥満に移行することはない。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
D
解説を見る