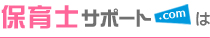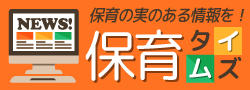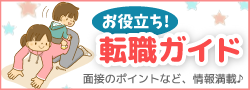保育士試験|オリジナル問題集
「児童家庭福祉」part1
-
第3回
オリジナル問題集
登録日:2014/11/06
「児童家庭福祉」 part1
問1
次に掲げた施設の中で児童福祉施設に分類できない施設が一つ含まれている、記号で答えなさい。
- 助産施設
- 母子生活支援施設
- 児童養護施設
- 児童自立支援施設
- 少年院
回答を見る
回答を閉じる
![]()
E
解説を見る
次の文は、児童福祉法の改正の要点が述べられています。誤った記述が一つ含まれています、記号で答えなさい。
- 昭和20年代の改正では、療育施設が、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設の3つの施設に分化し、その名称が児童福祉法からなくなった。
- 昭和30年代の改正では、精神薄弱児施設から精神薄弱児通園施設が独立し、さらに、情緒障害児短期治療施設が創設され、児童福祉施設が13種類となった。
- 昭和40年代の改正では、肢体不自由児施設に入所した児童については20歳まで、重症心身障碍児施設については社会生活に順応できるようになるまで、入所期間を延長することができるようになった。
- 平成2年の改正では、社会福祉関係八法改正の一環として在宅福祉事業の法定化が行われた。
- 平成20年の改正では、保護者からの相談に応じ情報提供及び助言を行う事業や保育所等において児童の養育を支援する事業など子育て支援の法定化が行われた。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
E
解説を見る
問3
次の文は、欧米の児童福祉の展開について述べられたものです。適切な記述を○、不適切な記述を×としてそれぞれ選びなさい。
- 政策としての福祉は、イギリスのエリザベス救貧法からはじまったといわれている。この法律は、社会福祉のみならず、その後、社会政策、社会保障の分野にも展開していく重要なものであり、その対象は、有能貧民と無能貧民とされており、児童を積極的に救済の対象とはされていなかった。
- 救貧法は1834年に大幅に改正される(新救貧法)。この新救貧法は、院内救済、劣等処遇、救貧行政の統一などの原則のもとに進められた。
- イギリスでは、1884年民間団体として全国児童虐待防止協会が設置され、1889年には児童虐待防止法の成立をみる。
- カーティス委員会報告に基づき、児童養護における保護は、第一義的に、養子縁組や里親制度で行うべきであるとの考え方が導入され、とりわけ乳児については、集団養護をできるだけ避ける方向が明確となる。
- ポーランドのコルチャックは、教育書、童話、戯曲、ラジオ番組などを通じて、児童の福祉と権利を訴え、それぞれ自ら実践した。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
×-○-○-○-○
解説を見る
問4
次の【Ⅰ群】児童福祉施設の名称と【Ⅱ群】施設の機能を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
【Ⅰ群】
- 児童自立支援施設
- 児童養護施設
- 乳児院
- 情緒障害児短期治療施設
- 母子生活支援施設
【Ⅱ群】
- ア.乳児を療育する
- イ.児童を単に保護するだけでなく、退所後の支援などを行い、児童の自立を支援する。
- ウ.児童の情緒障害を治す。
- エ.児童に単に養護するだけでなく、退所後の支援などを行い、児童の自立を支援する。
- オ.母子を保護し、その自立の促進のために生活を支援する。
(組み合わせ)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エ | ウ | オ | イ | ア | 2 | ウ | イ | エ | ア | オ |
| 3 | ア | オ | イ | エ | ウ |
| 4 | イ | エ | ア | ウ | オ |
| 5 | オ | ア | ウ | イ | エ |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
4
解説を見る
問5
次の文は、わが国の児童福祉の実施体制についての記述である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
児童の育成責任は保護者が有していることはいうまでもないが、 (A)も同様にその責任を有している。すなわち(B)や親子関係の不調等で保護者がその責任を果たすことが困難な場合には、 (A)は、保護者がその責任を果たせるよう必要な(C)を行うとともに、 このような(C)によっても児童の健全な育成が困難な場合には、 保護者に代わって(A)が直接児童の保護・育成にあたることとなる。
(組み合わせ)
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 親族 | 経済的な理由 | 保護 | 2 | 国・地方公共団体 | 夫婦関係 | 支援 |
| 3 | 国・地方公共団体 | 経済的な理由 | 援助 |
| 4 | 親族 | 夫婦関係 | 支援 |
| 5 | 国・地方公共団体 | 夫婦関係 | 援助 |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
3
解説を見る
問6
次の文は、児童相談所の業務について述べられたものである。その中で誤った記載が1つ含まれているが、それを記号で答えなさい。
- 子どもに関する各般の問題について家庭等からの相談のうち、専門的な知識、技術を必要とするものに応ずること。
- 調査、判定に基づき必要な助言を行うこと
- 児童の一時保護を行うこと
- 施設入所等の措置を行うこと
- 市町村相互間の連絡調整、市町村への情報提供、その他必要な援助を行うこと
回答を見る
回答を閉じる
![]()
B
解説を見る
次の【Ⅰ群】児童福祉施設の専門職の名称と【Ⅱ群】その専門職について述べたものを結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
【Ⅰ群】
- 保育士
- 児童指導員
- 児童自立支援専門員
- 児童生活支援員
- 母子指導員
【Ⅱ群】
- ア.児童自立支援施設において児童の生活支援を行う職員
- イ.母子生活支援施設において、母子の生活指導を行う職員
- ウ.地域の子育て支援の中核を担う専門職
- エ.児童自立支援施設において、児童の自立支援を行う専門の職員
- オ.児童養護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設等で、児童の生活指導を行う職員
(組み合わせ)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ア | イ | ウ | エ | オ | 2 | ウ | オ | エ | ア | イ |
| 3 | エ | ウ | オ | イ | ア |
| 4 | イ | ア | ウ | オ | エ |
| 5 | オ | エ | イ | ウ | ア |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
2
解説を見る
問8
次の文は、児童福祉援助の1つの過程である事前評価(アセスメント)について述べたものである。(A)~(C)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
アセスメントは大きく「(A)」と「(B)」という2つのプロセスに大別できる。
つまり、当事者に関する正確な(A)を行い、その情報に基づいて当事者の問題とニーズを明確にしたうえで、
客観的判断によって解決すべき課題の優先順位を決定する過程が「アセスメント」である。
まず(A)である。当事者が子どもの場合、子どもの生育歴、生活のようすなど、
また親の気持ちや反応などを子どもの親・家族から直接聞くことも必要である。
インテークと同様、子どもと家族の双方から偏りなく(A)を行うことが重要である。
次に(B)である。収集した情報から当事者のニーズ、抱えている問題を把握する。
さらにそこから解決すべき問題を限定し、その問題解決に向けて利用できる(C)を明らかにしていく。
この時、援助者は子どもと家族の双方が問題解決に向かう動機づけや能力を客観的に評価する必要がある。
(組み合わせ)
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 情報の収集 | 情報の分析・解釈 | 社会資源 | 2 | 情報の提供 | 情報の整理 | 法律 |
| 3 | 情報の加工 | 情報の開示 | 団体 |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
1
解説を見る
問9
次の文は、個別援助技術(ケースワーク)の内「面接」について述べたものである。1つだけ誤った記述があるが、それを記号で答えなさい。
- 「面接」とは、「目的をもった会話」「専門的な会話」を意味する。面接には、通常日常空間を用いることが望ましいと考えられている。
- 面接の第一条件は「傾聴」である。
- 児童福祉援助は、利用者との信頼関係の構築からはじまる。信頼関係を速やかに構築するには、相手の立場や思いに対する深い共感的態度が重要である。
- 援助者は、当事者のことばだけでなく、態度、反応、表情等の身体言語も深く観察し、当事者の感情の変化を把握する必要がある。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
A
解説を見る
問10
次の文は、保健所が行う児童福祉に関する業務について述べたものである。誤った記載が1つあるが、記号で答えなさい。
- 児童の保健、予防に関する知識の普及
- 児童の健康相談、健康検査、保健指導を行う
- 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育指導を行う
- 児童福祉施設で、献立の作成から、料理の提供を行う。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
D
解説を見る