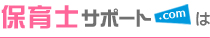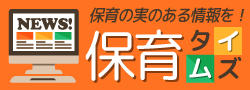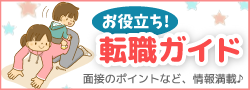保育士試験|オリジナル問題集
「保育の心理学」part5
-
第39回
オリジナル問題集
登録日:2016/04/18
「保育の心理学」 part5
問1
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
ゲゼル(Gesell,A.L)は、一卵性双生児に階段上りの練習を行い、環境は発達を促進させるが基本的な様態と順序は成熟によって決まるとし、成熟優位説をとなえた。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○
解説を見る
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
発達の流れには個人があり、細かく見ていくと、さまざまな筋道を通る。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○
解説を見る
問3
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
スキンシップを図ると、依存性の強い子どもになってしまい、大人になっても自立できないようになるので、立派な大人に育てるためにはスキンシップは必要ない。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
×
解説を見る
問4
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
生まれた直後の新生児は、最初は目が見えていないが、数日で成人並みの視力になる。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
×
解説を見る
問5
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
新生児から吸啜反応行動が備わっているが、これは食行動のひとつの基礎である。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○
解説を見る
問6
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
児童期は競争意識や共同意識(共同意義)が高まり、ドッジボールやサッカーなどのスポーツを好むようになる。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○
解説を見る
次の文は、子どもの発達と保育の実践について記述されたものである。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 吃音は、2~9歳のあいだに症状が現れ、自然に治ることも多い。
- 反応性愛着障害は、正常の環境下で育て直すことにより、症状は改善する。
- 反応性愛着障害は、自閉症で見られるようなこだわり行動が特徴である。
- 不登校の主たる要因は、学校に対する強い嫌悪感が形成されることである。
(組み合わせ)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | × | × | ○ |
| 2 | × | ○ | ○ | × |
| 3 | × | × | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | × | × |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
4
解説を見る
問8
次の文は、子どもの発達と保育の実践ついての記述である。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 摂食障害は一般に男性よりも女性に多くみられる。
- 摂食障害は過度の過食があっても、死亡することはない。
- 外傷性ストレス障害は、原因となる心的障害が5歳以前に受けたものである場合にのみ診断する。
- 多動性障害は、乳幼児期のしつけ不足が原因である場合が多い。
(組み合わせ)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | × | × | × |
| 2 | × | ○ | ○ | × |
| 3 | × | × | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | × | ○ |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
1
解説を見る
問9
次の文は、保育における発達援助について記述されたものである。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- トイレット・トレーニングの開始は、早ければ早いほど良い。
- 生活習慣は各家庭で異なるので、獲得の取り組みは保護者に任せておく。
- 第一次反抗期の子どもは、本当に大人に反抗しているのではないことをふまえ、対応することが大切である。
- 基本的生活習慣の獲得には、様々な要素が関係している。
(組み合わせ)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | × | × | ○ | ○ |
| 2 | × | ○ | × | × |
| 3 | ○ | × | ○ | × |
| 4 | ○ | ○ | ○ | × |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
1
解説を見る
問10
次の文は、保育における特別な配慮が必要な子どもへの対応について記述されたものである。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 延長保育や長時間保育が、子どもにどのよう影響を与えるかを考える必要がある。
- 子どもの障害を認めていない保護者には、できるだけ早く現実を受け止めるように伝える。
- 子ども障害には、身体障害や発達障害、知的障害など様々なものがある。
- 特別な配慮を必要とする子どもへの関わりは専門家だけに任せ、保育士は関与しない方が良い。
(組み合わせ)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | × | × | ○ | × |
| 2 | ○ | × | × | × |
| 3 | ○ | × | ○ | × |
| 4 | × | ○ | × | ○ |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
3
解説を見る