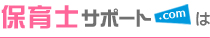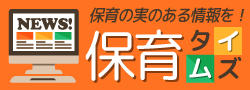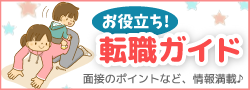保育士試験|オリジナル問題集
「保育原理」part6
-
第40回
オリジナル問題集
登録日:2016/05/09
「保育原理」 part6
問1
次の文は、「保育指針」の中の、子どもの健康支援に関する記述である。( A )~( D )に当てはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに( A )及び発達状態について、定期的、( B )に、また、必要に応じて随時、把握すること。
- 子どもの健康に関する( C )を作成し、全職員がそのねらいや( D )を明確いしながら、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めていくこと。
(組み合わせ)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 発達 | 継続的 | 保育課程 | 内容 |
| 2 | 発育 | 継続的 | 保健計画 | 内容 |
| 3 | 成長 | 継続的 | 指導計画 | 目標 |
| 4 | 発育 | 継続的 | 保健計画 | 目標 |
| 5 | 成長 | 断続的 | 指導計画 | 目標 |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
2
解説を見る
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
大正時代の託児所は民営のもので、就労している親から子どもを預かるだけであった。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
×
解説を見る
問3
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
糸井一雄は、「この子らの世の光に」と主張した人物である。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○
解説を見る
問4
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
我が国では、幼児教育にかかる費用の無償化は実現していない。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○
解説を見る
問5
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
マクミラン姉妹が創設した保育学校は、ドイツの保育学校のモデルとされた。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
×
解説を見る
問6
次の文を読み、適切なものには○を、不適切なものには×で答えなさい。
コダーイは民族音楽による音楽教育を創始した。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○
解説を見る
次の文は保育士の資格について記述されたものである。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 保育所では、職員一人一人が課題を持って主体的に学ぶことが必要である。
- 保育所の職員は、様々な信頼関係を形成していくなかで、常に自己研鑽に努め、喜びや意欲を持って保育にあたる必要がある。
- 保育士の資格を持たない者は、保育士を名乗ることも保育を行うこともできない。
- 子どもたちの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、保育所職員に責任感があればよい。
(組み合わせ)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | × | × | × | ○ |
| 2 | ○ | ○ | × | × |
| 3 | × | ○ | × | ○ |
| 4 | ○ | × | ○ | × |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
2
解説を見る
問8
次の文は「保育所保育指針解説書」の保育所の自己評価について記述されたものである。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 保育所の自己評価に用いる資料には、保育所が実施した様々な調査結果や寄せられた要望は含まれるが、苦情については含まれない。
- 評価の観点や項目は、評価に関する様々な情報を収集するなど、見直すことが大切である。
- 保育の質の向上のため、また保育所としての機能を十分に果たしていくために保育所の適切な評価の観点や項目を考えることが必要である。
- 第三者評価の評価項目の中から必要な物を選定したり、独自の評価項目をつくるなど、評価の観点や項目が各保育所に合った項目となるようにする。
(組み合わせ)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | × | ○ | ○ | × |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | × | × | × | × |
| 4 | × | ○ | ○ | ○ |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
4
解説を見る
問9
次の文は家庭的保育事業について記述されたものである。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 乳幼児を保育するための専用の部屋を設けなければならない。
- 家庭的保育事業の実施は、家庭的保育者の居宅または賃貸アパート等で、一定の要件を満たすもので、市町村長(特別区の区長)が適当と認めた場所である。
- 家庭的保育者だけで保育する場合は、乳幼児の数は3人以下でなければならない。
- 保育状況の把握のため、家庭的保育事業における連携保育所は、家庭的保育支援者に家庭的保育者の居宅などを少なくとも1ヶ月に1回以上訪問させなければならない。
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ○ | ○ | × |
| 2 | × | ○ | ○ | ○ |
| 3 | × | × | × | ○ |
| 4 | ○ | × | ○ | × |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
1
解説を見る
問10
次の文は、保育サービスの向上のための制度である第三者評価と騎乗解決のしくみについて記述されたものである。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 第三者評価は、入所児童の保護者などからヒアリングやアンケートなどで利用者の声を聞き、評価結果に反映させる。
- 都道府県社会福祉協議会に苦情を処理するための運営適正化委員会が設置されている。
- 評価の結果を知るには、都道府県に問い合わせなければならない。
- 利用者は、苦情があるときには、市町村または特別区の窓口に申し出る。
(組み合わせ)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | × | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | × | × |
| 3 | × | × | × | × |
| 4 | × | × | ○ | × |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
2
解説を見る