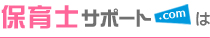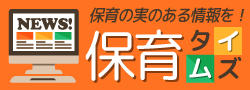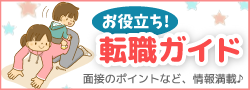保育士試験|オリジナル問題集
「保育原理」part1
-
第1回
オリジナル問題集
登録日:2014/11/06
「保育原理」 part1
問1
次の文は、諸外国の保育の歴史に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×としてそれぞれ選びなさい。
- オーベルラン(Oberlin,J.F.)によってドイツの一地方に設立された幼児保護所は、世界で一番古い保育施設である。
- オーウェン(Owen,R.)は、イギリスにおける産業革命の影響でこどもたちまでも労働にかりたてる社会改革のため、「性格形成新学校」を開設した。
- フレーベル(Frobel, F.W.)は、世界の幼稚園の原型となる、「幼稚園」(Kindergarten、1840)を創設した。
- マーガレット マックミラン(Margaret McMillan)は、1911年に戸外保育学校(Open-air Nersery School)を開いた。しかしこの保育学校は、教育をあまりに重要視したため、良家の子女しか利用せず、一般的な広まりをみせなかった。
- モンテッソーリ(Montessori,M)は、イタリア ローマのスラム街にある「子どもの家」で幼児期の教育に取り組んだ。モンテッソーリの教育は、子ども理解に基づいた内発的成長力への信頼によるものであり、自己教育の確立を目指すものであった。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
×-○-○-×-○
解説を見る
次の文は、日本の保育の歴史に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×としてそれぞれ選びなさい。
- 日本の保育の歴史は、明治9年(1876年)新潟静修学校内に守孤扶独幼稚児保護会の名のもとに整えられた託児施設の誕生がスタートである。
- 日本の企業内託児所の始まりは、明治27年(1894年)に東京紡績株式会社に付設されたものである。
- 明治32年(1899年)「幼稚園保育及設備規定」により文部省は、幼稚園の目的・内容・施設設備などについての基準を、国としてはじめて明確化した。
- 大正デモクラシーの思潮のなかで、自由主義的教育が進められ「生活を生活で生活へ」というスローガンに表わされる誘導保育論を提唱したのは、赤沢夫妻である。
- 昭和6(1931)年の満州事変から昭和16(1941)年の太平洋戦争の戦時体制下でも、保育ニーズの高まりはとどまらず、幼稚園の増設や普及は促進された。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
×-○-○-×-×
解説を見る
問3
適切な記述を○、不適切な記述を×としてそれぞれ選びなさい。
- 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設である。
- 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する保育士が、家庭との緊密な連携の下に、・・・子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特徴としている。
- 保育の対象は子どもだけでなく、子どもと共に暮らす保護者の支援もその範囲となる。
- 地域の様々な子育て上の困難を抱えている家庭の子育てに関する相談・助言を行うことも保育所(保育者)の守備範囲となる。
- 保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育するものである。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○-×-○-○-○
解説を見る
問4
次の文は、「保育所保育指針」第3章保育の内容のア生命の保持の一部である。( A )~( E )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 一人一人の子どもが、(A)に生活できるようにする。
- 一人一人の子どもが、(B)で(C)に過ごせるようにする。
- 一人一人の子どもの(D)欲求が、十分に満たされるようにする。
- 一人一人の子どもの(E)が、積極的に図られるようにする。
(組み合わせ)
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全 | 幸福 | 活発 | 心理的 | 好奇心 | 2 | 快適 | 健康 | 安全 | 生理的 | 健康増進 |
| 3 | 優雅 | 健康 | 安全 | 生理的 | 健康増進 |
| 4 | 安全 | 活発 | 自律的 | 3大 | 成長 |
| 5 | 快適 | 幸福 | 自律的 | 3大 | 好奇心 |
回答を見る
回答を閉じる
![]()
2
解説を見る
問5
次の文は、「保育所保育指針」第6章 「保護者に対する支援」についての記述です。適切な記述を○、不適切な記述を×としてそれぞれ選びなさい。
- 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援は、子どもの保育との密接な関連の中で、子どもの送迎時の対応、相談や助言、連絡や通信、会合や行事など様々な機会を活用して行うこと。
- 保護者に対し、保育所における子どもの様子や日々の保育の意図などを説明し、保護者との相互理解を図るよう務めること。
- 子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行う。
- 保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じ個別の支援を行うよう務めること。
- 保護者に不適切な養育などが疑われる場合には、市町村や関係機関と連携と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ること。また虐待が疑われる場合は、速やかに保護者と話し合いの場を設け、事態の改善を図る。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○-○-○-○-×
解説を見る
問6
次の記録は、保育の実践上の記録です。実践上の記録として誤っているものを一つ選びなさい。
- 保健計画
- 週案
- 身体測定記録
- 家庭連絡帳
- クラス便り
回答を見る
回答を閉じる
![]()
C
解説を見る
「保育所における食育に関する指針」では発達段階に応じた食育のねらいと内容が示されてます。3歳以上児では5項目が設定されており、次の文は、その内料理と食に関して述べたものです。適切な記述を○、不適切な記述を×としてそれぞれ選びなさい。
- 料理をつくる人に関心を持つ
- 食事を催促したり、要望を伝える
- 食事の準備や後片付けを見て関心を持つ
- 自分で料理を選んだり、盛り付けたりする
- 出来上がった料理を、見て、嗅いで、触って、味見する。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○-○-×-○-×
解説を見る
問8
次の文は、子育ての社会的支援と保育所の役割についての記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
- 現代の一般的な家族構成では、家族だけで子育てをしていくことが困難な状況にあり、どのようにして、一昔前のような大家族への構成変化を促していくかが課題である。
- 宮参りや七五三などの祝い事が形骸化し、子育ての社会的な結合が失われてしまった現在では、新しい時代にふさわしい祝い事や行事などの社会的な結合を早期に生み出す必要がある。
- 子育て支援とは保護者(家庭)を中心としつつも、家庭のみにまかせることなく、国や地方公共団体をはじめとする社会全体で責任をもって支援していくことである。
- 国は子育てを社会全体で責任をもって支援していくという方向性は示したが、指針などへの明文化には消極的な姿勢を変えていない。
- 今日の保育所は、入所児童やその保護者のみ支援の対象としているが、今後は地域の一般家庭の乳幼児やその親へと、活動対象を広げることが検討段階に入った。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
C
解説を見る
問9
次の文を読み、内容が適切であれば○、不適切であれば×で答えなさい。
「児童の権利に関する条約」(1989年国連)の第18条には、「父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する」とあり、子どもを育てる責任は、父母(保護者)にのみ存することが明確に示されている。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
×
解説を見る
問10
次の文を読み、内容が適切であれば○、不適切であれば×で答えなさい。
保育の原理を考えるとき、養護と教育に関わるさまざまな側面を認識することが必要である。
回答を見る
回答を閉じる
![]()
○
解説を見る